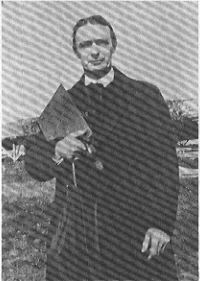No.17(1989.5.25)p 8-10 No.17(1989.5.25)p 8-10
Rudolf Steimer(1861-1925)の400巻ちかい全集が本学中央図書館に入庫したのは、つい3年前のことである。日本ではじめてシュタイナーの思想にふれ、シュタイナーの設計したゲーテアヌムを実地に訪れ、圧倒的な感動を受けて帰った人物が、早稲田大学の故今井兼次教授であったことを思うと、この大部な善著作が今井教授の亡くなる直前に早大図書館に届いたことに、何か運命的なものを感じる。 シュタイナーは、だから日本ではまず1920年代に建築畑の人に知られたわけだが、その後戦争をはさんで、一部の教育家、神秘主義者たちなどのあいだで話題になり、やがて70年代あたりから「シュタイナー学校」の存在を通じて広く一般に注目されるようになった。日本の学校教育の問題を反映して、日本の世論はシュタイナー教育のいわゆるユニークさという現象面にばかり目をうばわれる状況が続いていたが、そのなかで背景の理念をなすアントロポゾフィーという思想にも取りくもうとする関心が徐々にめざめ、ここにようやくシュタイナーの全体像をめぐる研究活動が始まったのである。そのとき、いちはやく本学図書館に資料がそろえられた事実は、まことによろこばしい。
従来の学問形式にとどまりつつ新しい内容を語るという、この慎重姿勢が1900年を境にして堂々と大胆になる。彼ははっきり「超感覚世界」という言葉を公の場で口にする。『テオゾフィー』では、人間が肉体をもつ物理世界と、感情のとりこになる魂世界と、永遠の法則を認識しうる精神世界との三重性の中にいることを示し、物理世界以外は「超感覚世界」だが、修業によってこれをも知覚することができる、と説いた。そして人間の自我は、肉体が亡びても精神世界に帰り、また次の肉体にやどって地上に生きる日がくる、という転生論までくりひろげた。 『テオゾフィー』は、版を重ねに重ね、今日なおシュタイナーを学ぶ人が最初にひもとく入門書であるが、世紀の初めにひとたびこれを発表してからというもの、シュタイナーの著作・講演のすべては超感覚世界を前提とした立論になりかわる。まかりまちがうと無責任なオカルトに堕しかねないことがらを、現代人のさめた目で納得して受けいれられる修業方法、それが緊急な課題だと考えて、彼は1904年から翌年にかけて『いかにしてより高次の世界の認識を得るか?』を著した。『アカシャ年代記』(1904−1908)、『神秘学概論』(1910)の両著では、彼の超感覚描写は地球自体の転生論にまでおよび、通常の自然科学論理ではとうていつかみえない叙述が並ぶばかりとなる。 1910年代にはいると、個々の人間が転生をくりかえす際に背負っていくもの、つまり前世から未来世へのカルマといったものへの考察が多くなり、これを舞台劇の形式で表現した四部作『神秘劇』(1910−1913)が著される。この種のやや文学的なカルマ探究は、ゲーテの「ファウスト」や「メールヒェン」をめぐる講演・解説などの形でも頻繁におこなわれる。
1925年にこの世を去るシュタイナーは、20年代にはいるとすでに晩年になっているわけだが、ここで彼は従来の諸領域にわたる活動をいっそう展開すると同時に、新たに医学と農業への考察をおこなっている。1924年の農業講座記録、25年のイタ・ヴェークマンとの共著『精神科学認識によって治療技術を拡大する基礎』は、生涯の最後を飾る二大業績となった。64歳という享年を覚悟していたのかどうか、シュタイナーは、死の2年前から自叙伝『わが人生の歩み』を、週刊「ゲーテアヌム」に連載し、これは死後2巻本にまとめられた。 さて、いわゆる学者の肩書をつけてかまわないシュタイナーだが、その業績をもとにして現実の社会にさまざまな実践活動がひろがった、という点では彼はかなり型破りな学者である。シュタイナー学校が生まれ、障害者村がいとなまれ、病院、薬局、農場がふえている。建築・インテリア・デザイン、衣服、食事の分野にま彼の思想を浸透したものがある。さらには利子・利息をたがいの話し合いで決めたりする銀行もある。つまりは全体として大きな世直し運動になろうとする試みなのだ。そのいずれかに、ふとした機会に出会う人は多い。 まずは何かの社会現象に出会って、その背後にシュタイナーの思想があると知る。ではその思想を読み解こう、と思って彼の著作集の前にたたずむ人は、ぼうぜんとするだろう。何から手をつけてよいのか―。もちろん、各自の出会った分野からはいってよいのである。ただ、次の段階で少なくとも心がけて欲しいのは、あるバランスをとりつつ彼の全体像をもつことである。1900年以前の著作と以降のそれ、社会実践面と個人の内的修業面―これらが片面にのみかたよることのないように、と、私自身15年ほど牛の歩みで取り組んできてのささやかな助言である。 Copyright (C) Waseda University Library, 1996. All Rights Reserved. Archived Web, 2002 |